本書は動物心理学からネコの心の進化を解明。ミステリアスなネコの思考能力を独自研究で探る。物理法則理解、飼い主認識、推論能力を家庭・猫カフェの500匹で検証。ネコは柔軟に考え、ヒトとの共生で進化したことがわかる。

体裁
四六判/上製/192頁。初版年月日:2022/09/24。ISBN:978-4-7664-2843-8 (4-7664-2843-9)。Cコード:C0045。定価 2,200円(本体 2,000円)。
もくじ
- はじめに
- 第1章 動物はどのように考えるのか
- 1 考えるのに言葉はいらない
- 2 動物の思考研究 3つの推論能力
- 3 多様な種を比較する〝ものさし〟
- 第2章 ネコはどこまで物理法則を理解しているのか
- 1 動物はどのように〝物理的に考える〟のか
- 2 ネコは本当に物理的な推論が苦手なのか
- 実験1: 音からモノの存在を推論できるか
- 実験2: 動きと一致する音からモノの存在を推論できるか
- 実験3: 物理的に〝ありえない結果〟にどんな反応をするか
- 実験4: 飼い主の声から位置を推論できるか
- 実験5: 物理的な音を再生するとどうなるか
- 第3章 ネコは〝声〟から‶顔〟を思い浮かべるのか
- 実験1: ネコは飼い主の声から顔を予測するのか
- 実験2: ネコは同居ネコの名前と顔が分かるのか
- 第4章 ネコは〝どこに〟‶何が〟を思い出せるのか
- 実験1: エサはどこに行った?
- 実験2: あのエサはどこに行った?
- 終章 ネコの思考能力はどのように進化したのか
- 1 ネコ研究の最前線
- 2 ネコの思考能力はなぜ進化したのか
- 3 これからの動物の思考研究
解説
本書『ネコはここまで考えている:動物心理学から読み解く心の進化』は、ネコ心理学者である高木佐保氏が、10年にわたるネコの認知研究の集大成としてまとめた一冊です。ネコは伴侶動物として世界中で人気を博していますが、そのミステリアスで何を考えているかわからない魅力が、逆に認知能力の研究を遅らせてきました。著者は、比較認知科学の観点から、ネコの思考能力を科学的に解明し、ヒトとのより良い関係構築を目指します。ネコの心を「認知」と定義し、感情ではなく、刺激の知覚・判断・推論能力に焦点を当てています。これにより、ネコが思っている以上に柔軟で高度な思考を持っていることを明らかにします。
まず、ネコ研究の背景を理解する必要があります。ネコは約9500年前からヒトと共生してきましたが、研究はイヌや霊長類に比べて少なく、能力が過小評価されてきました。その理由として、ネコの性格が挙げられます。ネコは知らない人や装置を見ると隠れたり逃げたりするため、実験室での研究が難しく、伝統的な視覚中心の実験パラダイムが合わないのです。一方、イヌはトレーニングしやすく、fMRIなどの脳画像診断も可能で、研究が進んでいます。高木氏はこの格差を指摘し、ネコの聴覚優位性を活かした独自の方法を開発しました。対象は家庭飼育のネコや猫カフェのネコなど約500匹で、ストレスを最小限に抑えたゲームのような課題を実施。生育環境の違い(一匹飼い、多頭飼い、カフェなど)を考慮し、協力飼い主を募って行いました。これにより、ネコの自然な行動を基にした信頼性の高いデータを得ています。
第1章では、動物の思考の基礎を解説します。動物は言葉を使わずとも考えます。著者は、動物の思考を3つの推論能力(物理的推論、社会的推論、クロスモーダル推論)で分類します。物理的推論は因果関係の理解、社会的推論は他者の行動予測、クロスモーダル推論は異なる感覚間の連想です。これらを種間で比較する「ものさし」として、進化史を読み解きます。ネコは捕食者として音に敏感で、獲物の位置を予測する能力が優れているため、聴覚を活用した実験が鍵となります。
第2章はネコの物理法則理解に焦点を当てます。従来、ネコは物理的推論が苦手とされていました。例えば、紐引き課題では、報酬付きの紐を選ばないため、因果関係を理解していないと結論づけられました。しかし、高木氏はこの実験の問題点を指摘します。ネコは紐自体に興味を持ち、報酬の有無に関わらず反応するのです。また、視覚中心の課題がネコの聴覚優位性を無視していました。そこで、音を使った実験を実施。実験1では、音から隠れたモノの存在を推論できるかを検証し、ネコが物理法則を理解していることを示しました。実験3では「ありえない結果」(例: 音がするのにモノがない)に対し、ネコが驚く反応を示し、期待値に基づく推論を確認。実験4では飼い主の声から位置を推論し、社会的側面へ移行します。これにより、ネコは「誰がどこにいるか」を考え、飼い主を個別に認識していることがわかります。物理から社会的推論への橋渡しが、ネコの柔軟性を強調します。
第3章では、クロスモーダル推論を探ります。ネコは声から顔を思い浮かべるのか? 実験1では、飼い主の声と顔の一致をテストし、ネコが予測する能力を確認。実験2は革新的で、同居ネコの名前と顔を区別できるかを検証。結果、ネコはヒトの言葉を理解し、名前から特定のネコを連想します。これはネコの言葉理解を科学的に証明した初の研究で、家庭環境の影響が大きいことが明らかになりました。多頭飼いのネコは特にこの能力が高く、共生生活が認知を進化させた証拠です。
第4章は記憶のメカニズムに着目。ネコは「どこに何があるか」を思い出せますか? 実験1ではエサの場所を記憶し、再現するかをテスト。実験2は偶発的記憶(たまたま覚えたもの)を検証し、ネコが柔軟に思い出す能力を示しました。これは高度な認知で、ヒトのエピソード記憶に似ています。ネコの記憶は短期・長期両方があり、狩猟本能と結びついています。
終章では、ネコの思考進化を総括します。ネコ研究の最前線として、著者の業績(2017年京都大学総長賞受賞)を紹介。ネコの能力はヒトとの共生で進化したと結論づけ、野生ネコとの比較を提案します。将来的には、適切な飼育法につながり、ネコの幸福を高めると展望します。
全体を通じて、本書はネコの魅力を科学的に深掘りします。著者の情熱が伝わり、読むとネコがより好きになるはずです。ネコはきまぐれではなく、複雑な思考を持つパートナー。ヒトのバイアスを捨て、ネコの視点で考える重要性を教えてくれます。この解説は、ネコ愛好家だけでなく、動物心理学に興味がある人にもおすすめです。
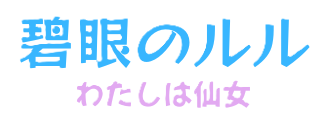

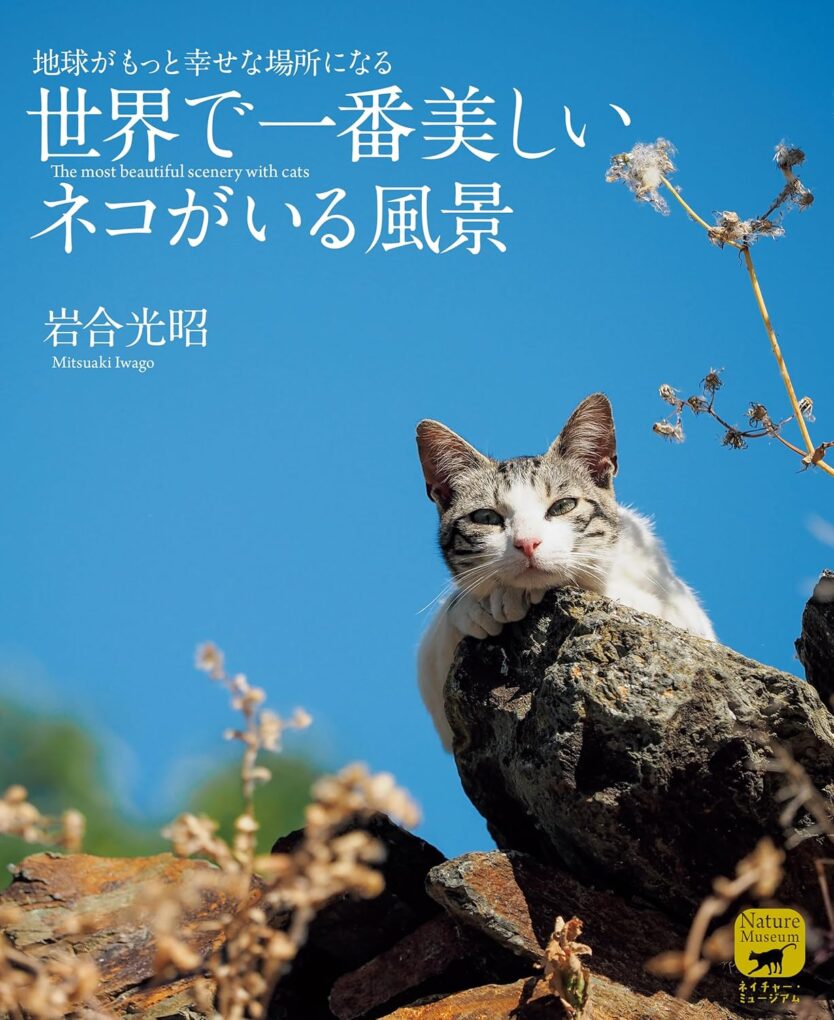
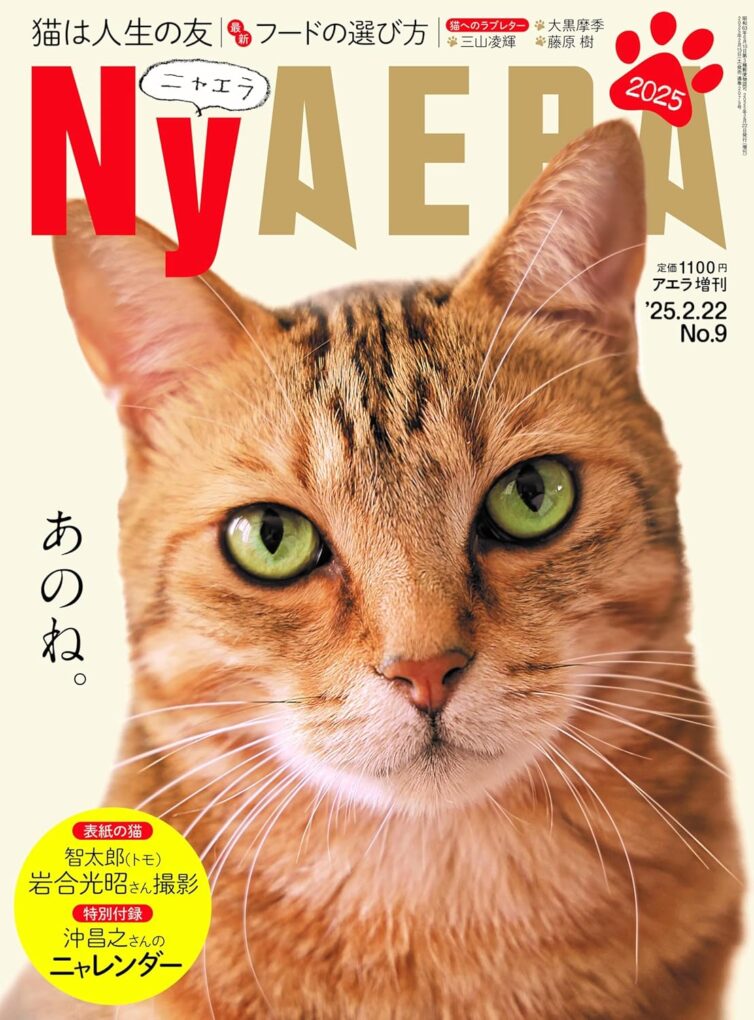
コメント・あしあと