『私が死んだあとも愛する猫を守る本』は富田園子の著書で、猫の飼い主が自身の死後や要介護状態になった場合に、愛猫の未来を守るための具体的な準備方法を解説した一冊です。猫に遺産を相続する方法、遺言書の書き方、「うちの猫ノート」の作成、老猫ホームの選び方、ペット信託の活用など、猫を守るしくみ作りを網羅。イラストははしもとみお、監修は磨田薫。

体裁
- 単行本(ソフトカバー)
- 本文128ページ
- ISBN 9784528024632
- 定価:1650円(10%税込み)
- 2025年2月4日初版発行
- 出版社:日東書院本社(辰巳出版)
もくじ
- はじめに
- 第一章 自分の身に何かあったとき、愛猫を託せる人はいますか? 現実にある、悲しい事件/万一のとき、愛猫を託せる人はいますか?/愛猫にいくら残せばいい?/頼れる人がいない場合は老猫ホームや愛護団体を探す/猫といっしょに入れる高齢者施設もある/貯えがない場合は保険を活用しよう/猫の健康管理も欠かせない
- 第二章 必ずしておきたい手続きと書類作り 「うちの猫ノート」に愛猫のデータをまとめよう/自分の「エンディングノート」を作ろう/猫のための〈遺言書〉を作ろう/〈遺言書〉を書かないとどうなる?/「負担付遺贈」をするための〈遺言書〉/より強力なセーフティネット〈ペット信託〉/〈ペット信託〉の契約書の作り方/〈信託契約書〉といっしょに〈遺言書〉も作ろう/〈信託契約書〉を作ったけれど、自分で愛猫を看取った場合はどうなる?
- 第三章 命のバトンタッチを成功させる 自分が倒れたらすぐに気づいてもらうシステムを作ろう/自宅で人知れず倒れたとき気づいてもらうためには/自治体の見守り制度を調べてみよう/地域担当の民生委員さんとつながっておこう/緊急連絡カードをつねに携帯&部屋に貼っておく/スマホアプリを活用しよう/玄関の鍵を開けてもらう方法を考えておく/愛猫を託す人には猫に会いに来てもらう/猫を託す人がすぐに駆けつけられない場合/新居へ移動するときの猫の捕まえ方を考えておく/弁護士や行政書士と「見守り契約」を結ぶ方法もある
- column ▪ 動物環境・福祉協会 Eva 理事長 杉本彩さんに聞く高齢者とペット問題 ▪ ペット信託で保護猫カフェに来たあずきちゃん ▪ 飼い主さんの入院で保護猫カフェに来たヤマトくん ▪ 愛護団体が支える高齢者とペットの暮らし
- 書き込み式「うちの猫ノート」
解説
本書は、猫の飼い主が直面する「もしものとき」の不安を解消するための実践ガイドです。著者の富田園子さんは、日本動物科学研究所会員で、猫の福祉やペットの終活に関する研究者として知られています。主な著書に『猫を飼う前に読む本』や『猫と一緒に生き残る防災BOOK』などがあり、自身も7匹の猫を飼っています。イラストを担当するのは、木彫り彫刻家のはしもとみおさんで、温かみのあるイラストが本書の魅力を高めています。監修はペット信託専門の行政書士、磨田薫さんが行い、法律面の正確性を確保しています。
はじめにでは、飼い主が元気なうちに愛猫を守る「しくみ作り」の重要性を強調します。高齢者だけでなく、一人暮らしの若い飼い主も対象で、事故や災害時のセーフティネットを構築することを促します。愛猫を路頭に迷わせないための準備が、飼い主の心の平穏につながると説きます。
第一章では、現実の悲しい事件を例に挙げ、飼い主の突然の死や入院で猫が保健所送りになるケースを紹介。愛猫を託せる人を探す方法を詳述します。家族や友人がいない場合、老猫ホームや愛護団体の活用を勧め、事前の見学や契約のポイントを説明。猫と一緒に暮らせる高齢者施設の情報も提供します。お金の面では、猫の生涯費用(医療費、食費など)を計算し、相続の目安を示します。貯蓄がない場合は、ペット保険や生命保険の活用を提案。猫の健康管理として、定期健診や病気の予防を強調し、長寿を支える基盤を築く重要性を説きます。この章は、読者が自身の状況を振り返るきっかけとなり、具体的な行動を促します。
第二章は、手続きの核心で、書類作りのステップをわかりやすくガイドします。まず「うちの猫ノート」の作成を推奨。これは猫の性格、医療歴、好物、日常習慣をまとめたノートで、緊急時に託す人に渡せばスムーズな引き継ぎが可能になります。テンプレートが付録としてあり、書き込み式で実用的です。次に自身の「エンディングノート」を作り、資産や希望を整理。猫のための遺言書の書き方を、行政書士監修のもとでステップバイステップで説明します。遺言書を書かないリスクとして、猫が相続人なしで保護施設行きになる可能性を指摘。「負担付遺贈」という方法を紹介し、お金を条件に猫の世話を託す遺言のサンプルを提供します。
さらに、より強力なツールとして「ペット信託」を詳述。信託は、猫の世話とお金の管理を信託会社や専門家に委託する仕組みで、飼い主の死後や要介護時にも継続的に機能します。契約書の作り方、必要書類、費用、信託の種類(金銭信託や不動産信託)を解説。遺言書との併用を勧め、飼い主が先に猫を看取った場合の残金処理も説明します。この章は、法律の専門用語を避け、図解や例を交えて初心者でも理解しやすく、読者が「これなら自分でもできる」と感じる内容です。
第三章は、命のバトンタッチの実践編で、飼い主が倒れた場合の即時対応に焦点を当てます。見守りシステムの構築を勧め、自宅での孤立を防ぐ方法を多角的に提案。自治体の見守り制度(例: 高齢者見守りネットワーク)の利用、地域の民生委員とのつながり、緊急連絡カードの作成と携帯、スマホアプリ(位置情報共有や緊急通報機能)の活用を詳述します。玄関鍵の共有として、鍵ボックスや信頼できる近隣住民への預け方をアドバイス。愛猫を託す人には定期的に猫に会いに来てもらい、信頼関係を築くことを促します。
託す人が遠方の場合の対応として、一時的な保護先の確保や輸送方法を説明。新居への移動時の猫の捕まえ方として、キャリーバッグの慣らしやストレス軽減のTipsを提供します。より確実な方法として、弁護士や行政書士との「見守り契約」を紹介。これは定期訪問や緊急時の対応を契約化するもので、費用対効果が高いと評価します。
コラムでは、動物環境・福祉協会Eva理事長の杉本彩さんのインタビューを収録。高齢者とペットの問題を深掘りし、保護活動の実態や政策提言を共有。実際の事例として、ペット信託で保護猫カフェに来た「あずきちゃん」の物語や、飼い主入院で預かった「ヤマトくん」のエピソードを紹介。これらは読者の感情を揺さぶり、準備の必要性を実感させます。また、愛護団体の支援事例を挙げ、高齢者の孤立防止と猫の福祉向上の取り組みを解説。
全体を通じて、本書は「今から準備しよう」という行動喚起を繰り返します。難解な法律話も平易にまとめられ、イラストが視覚的にサポート。読後、読者は具体的なアクションプランを立てられるでしょう。おすすめは、一人暮らしの高齢者、多頭飼いの方で、猫を絶対に困らせたくないすべての人。猫の一生を責任を持って守る「しくみ」を構築するための必読書です。
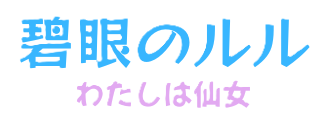

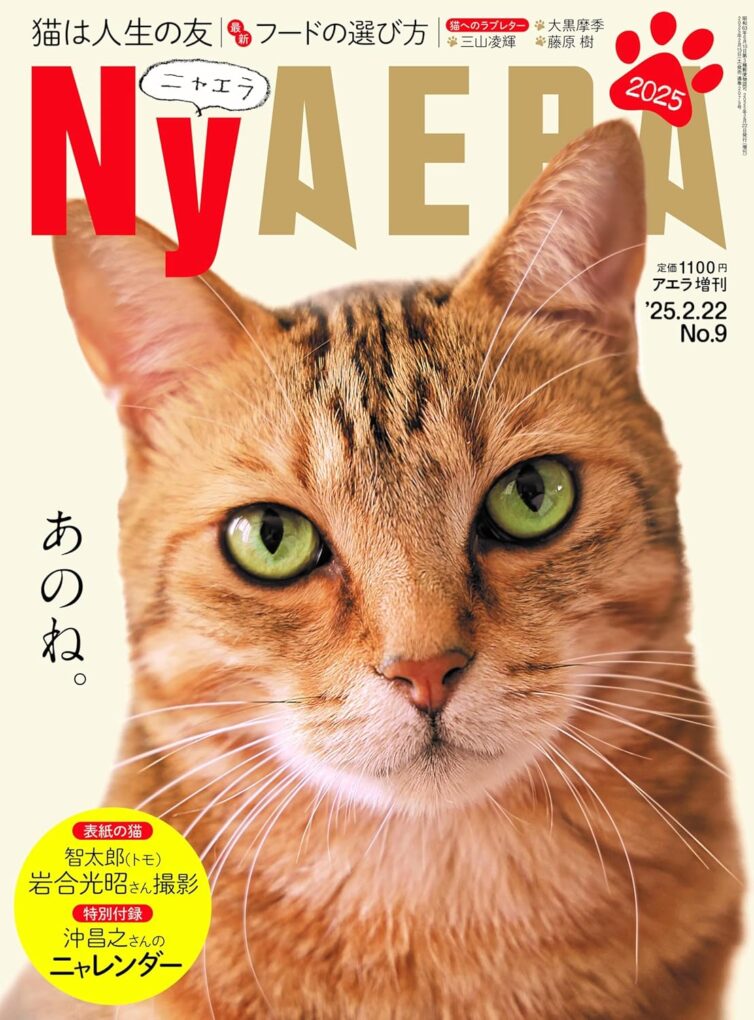
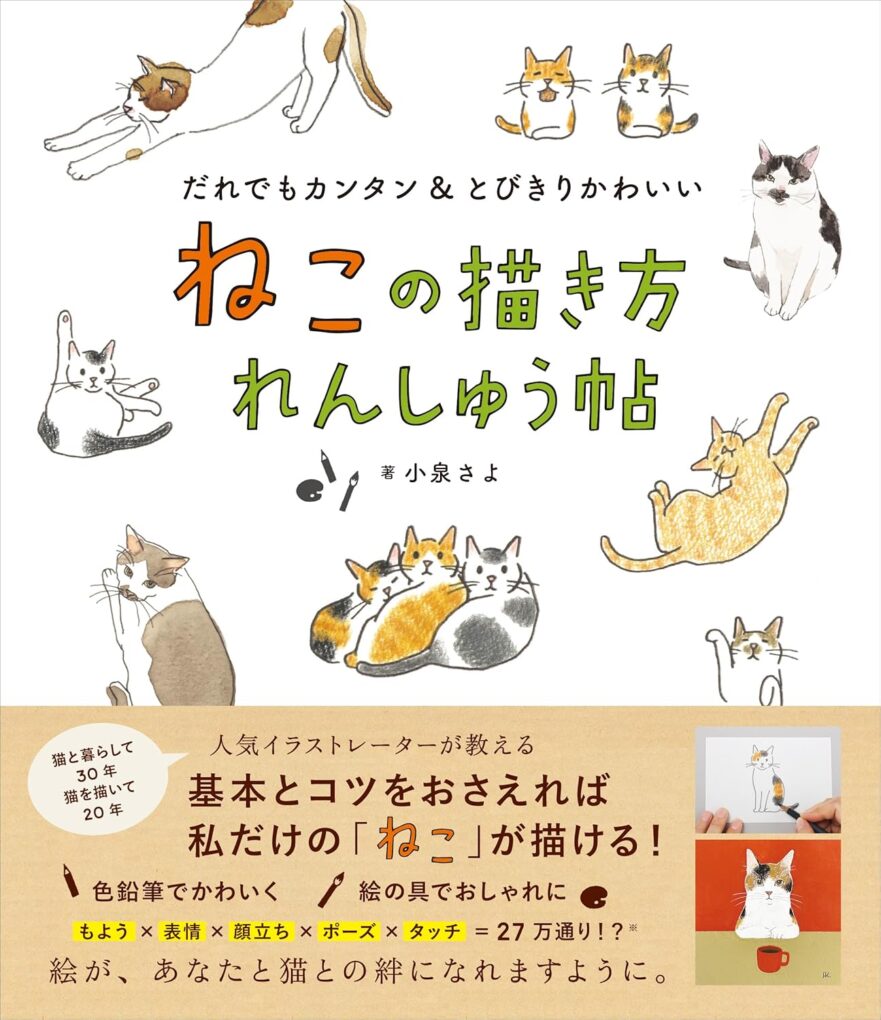
コメント・あしあと